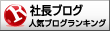戦後の教育の基本は「詰め込み教育」と一般的には言われている。
知識をひたすら詰め込み記憶して答えることばかりさせられて、反抗して真剣に学ぶことをしなかった。
なぜかというと、思考して自分なりの考えや視点がなければ、現実の課題をどう解決するか考えられなくなり、不安が募る感じがしたからだ。
クイズ番組に出て記憶をたどって答えることで課題解決できるならそれもいい。
しかし現実は違う。
課題には損得や善悪もからむし、自分の好き嫌いもからんでくるので、
基本は人間の対応できる能力を学んだり、あるいは自然や社会の法則を十分理解して課題解決方法を創造して実行し乗り越えなければならない。
唯物弁証法は
1.原因=対立物の統一、相互浸透の法則
2.プロセス=~量質変化の法則
3.結果=二重否定の法則
以上のように学んで、「知的メタボリック」(知識を完全に記憶しコンピュータに成る人)になるが、これは客観性と言われたが、実は活力が失われるし、思考力や創造力が抑えられる。
確かにマルクスの言ったことは冷静に現実をモノとしてどう変化するかの法則であるかもしれないが、物にも人間にも心がある。心には動きや作用、意味という目に見えない意志がある。
それを私は「唯心弁証法」と名づけているが、心で思うことが行動となる法則だ。
1.原因=矛盾が生じ感じる思いの法則(物は環境変化)
2.プロセス=質量変化の法則(思いが肉体的行動を創造しながら動く)
3.結果=より高い思いへ現実の思いを否定する二重否定の法則
この唯心弁証法がなされて後、唯物弁証法的に行動し解決するが、すべてが完璧に解決する法則ではない。
あくまでも、思いが未来をひらきより高次元の発展、成長するように、すべて物のはできていると同時に必ず「死」というようにエントロピーの法則が働く。
ところが人間が人工的に創作した制度やモノは死はない。
持続させるための変化、改造、改革があるのである。
人間は一代限りであるがゆえに「永遠」を実現させたいのに違いない。
さて、哲学的な持論はさておいて、知識は思考があってこそ生きるし、記憶は創造あってこそ生きると確信する。
人間の文化はハイブリットにできている。
だから詰込みの記憶だけに偏った教育には納得がいかなく基礎的な知識がない。
初めて社会に出たときの戸惑ったのは基礎的な知識がなさ過ぎて、現実の社会の出来事の課題が解決できない自分を知った。
そこからが大変で、基礎的な言語知識を学ぶ必要を感じ中学校の教科書を紐解いた。
もう一つ大事なことは脳の仕組みだ。
人間の脳は記憶の扉が開きっぱなしではない。忘れることしないと新しい知識が入らない。
それをつかさどっているのが、レム睡眠だ。
睡眠中に忘却作業をしてくれるようにできているそうだ。(今の科学の発展は凄い)
だから一番いいのは朝モノ考えるのがよくて「枕上の時観」というらしい。
最もクリエイティブな時間だそうです。(参考図書・思考の生理学-外山滋比古)
皆さんはいかが考えられますか?

「唯物弁証法」に思う
投稿日: