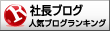ヨーロッパの中世はキリスト教の世界であった。
ルネサンスは神からの開放である。
そこで人間が自然を支配し利用することが正当化された。
「我思うゆえに我あり」とデカルトは言った。
しかし人間界では支配する側と支配される側と分類し対立させ考える。
この対立関係から開放させるためにマルクスの階級闘争の哲学が生まれる。
欧米の歴史では一方で個人主義を生み出し、
対立構造をなくすべく人権論争が巻き起こる。
理性の範疇では一理あるかもしれないが、
対極的に互いが助け合うという関係から理性至上主義だけでは解決できないのも事実だ。
今こそ東洋的なものの見方がキーワードになると感じる。
日本には佐久間象山や、山田方谷を育てた佐藤一斉という人物がいた。
彼の著書に「言志録」と言うのがある。
42歳(1813年)から82歳(1853年)まで費やされ書かれたものだ。
言志録2条に、
「太上は天を師とし、
其の次は人をしとし、
其の次は経を師とす。」
意味=最上の人は「天地自然」を師と仰ぎ、
其の次は「尊敬する人」を師と仰ぎ、
其の次は「教え」そのものを師とする。
一斉は志を持たねば学問をしない、
また志を立てて成功するには「恥」を知ることだと諭す。
この東洋的な武士道といわれる気質が庶民に至るまでいきわたっていたのが江戸時代だ。
京都では石田梅岩の「石門心学」を学ぶ塾は数箇所会った。
私が拘ってきたのは「人としてどうあるべきか」と自問自答してきた。
背筋のまっすぐな筋の通ったことを一貫(哲学がぶれない)して行動する人物に憧れを持った。
自分ではそんな人のそばにいて、少しでも学べば自分が磨けると考え師を求めたのであった。
「求めよさらば与えられん」ではないが、23歳のときに師と仰げる人物に出会った。
実に幸せだと感じるが、人間は寿命がある故別れもある。(平成五年に亡くなられた)
最近、恩師小田切瑞穂先生の良く話された言葉を反復し思い出していると、
先生は何を師として「潜態論」という哲学を体系化されたか考えるようになった。
理論物理学が専門の自然科学者であるから、自然が師だったに違いない
まさに佐藤一斉の言う「太上の人」である。
人にこだわってきた私は、今後は自然を師とすることをもう一度挑戦してみる。
実にわくわくするのと同時に、恩師と同じ目線で考えれる喜びが湧いてくる。
皆さんの師匠は誰ですか?