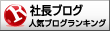「論語を楽しむ会」と言って故村下好伴先生の講義を10数年受けていた。
人間社会で生きていくには学而第一の「学びて時にこれを習う」がすべてで、生きていくには学ばなくては自己形成もできないし、課題解決もできない。
ましてや人間関係を、和を以て調和するのは難しいことだ。
論語は随所に処し方を教えてくれる。
例えば「過ぎたるは及ばざるがごとし」なんでも程々ということだが、議論でも盛り上がると言い過ぎて相手をへこますとこまでやってしまうし、食べ物や楽しいことも、もっとやりたいとブレーキがかからないのが人情だと、ついつい行動が行きすぎて、後悔するようになる。
「仁」の心少なし。
孔子は「仁」思いやりの心を持つことを柱に道徳、倫理を説く。
社会人になって必要な規範を磨くことは重要だし、体得しなければと学んだ。
そんな時期には老荘を読む気にならなかったのは、社会人として生きるには「無為自然」などと、悟り切ったような生き方には共鳴しにくいと感じていたからだ。
現実は競争社会で単に物事の考え方だけでは生きられないし、経済的な利害のことも実現しなければならないからだ。
最近、老荘を学ぶ機会を得て、「無為自然」となんでも自然に振舞うことで良いということかと思ったが、
「天鈞に休む。是を之れ両行と謂う」
天鈞は天に測って、両極端を知って判断するという意味だ。
ちなみに両行=「善は急げ」と「急がば回れ」「嘘も方便」と「嘘つきは泥棒の始まり」「大は小を兼ねる」と「山椒は小粒でピリリと辛い」のように対立する意味合いのことわざが必ずある。
古人は我々が両極端の考え方を両方踏まえたうえで、現実的な判断は直感的で決めると教えている。
言い換えると仏教では「中道」と言い、儒教での「中庸」とは違う。
「中庸」は極端に近づかない。
「中道」は両極端を知ったうえでないと歩めない道だ。
禅は大いにこの考え方を取り入れた。
たとえで、猿回しの話がある。
「ある猿回しが、飼っている猿たちに朝三つ、暮れに四つの団栗をやるぞといった。
猿たちが大層怒ったので,それなら、朝四つ、暮れ三つやることにしようといった。
すると猿たちは大層喜んだという。この話は詐術を用いて人を愚弄する話だ。」
一般の辞書ではそう解釈するが、老荘の「両行」は違う。
物事の本質は知らねばならないが,一般にそう思っているならそれでいいという。
世間一般の価値観に逆らうのも愚かなことだというのである。
このふたつのバランスをとっていくことは人生上手くいくことだと教えるのが「両行」だ。
これを学び老荘は単に自然の法則に従うことを良しとするのでなく、本質をしっかり押さえたら、左右にこだわる次元より、どちらもOKという「無の無」なるなる姿勢だ。
なんでも正直に言うのは馬鹿正直、老子は「知りて知らずとするは尚なり」と言っているのも「両行」だ。
善悪の価値観は天地にない、本来の自分の命に立ち返り淡交(利休の茶の湯の精神)な生き方すれば、人間はいくら使っても疲れないということだ。
道元禅師は「命」の活動を、
「春は花、夏ホトトギス、秋は月、冬雪さえて、冷しかりけり」と詠んでいる。
皆さんは命の価値観に立っておられますか?

「老荘」に学ぶ
投稿日: